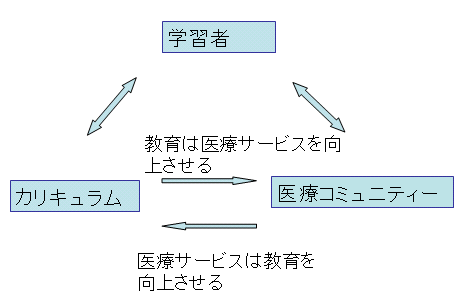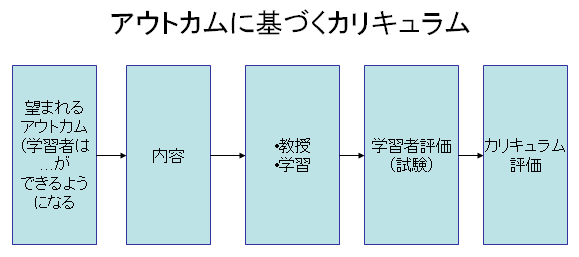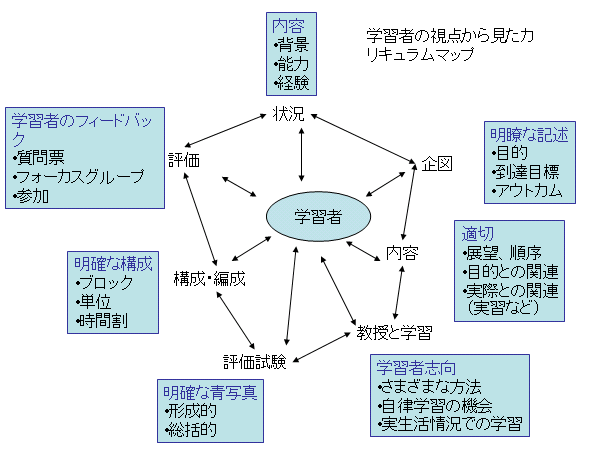カリキュラムデザイン
カリキュラムとは何か
・カリキュラムは実行される教育構想を表わすものである。
・学習コースあるいは教授細目(シラバスsyllabus)を意味するものと受け取られるようになった。
・学習者が何を知るべきか、どのように知るようになるかについての一連の価値と信念により裏打ちされている。
力リキュラムの3つのレベル
・計画された力リキュラム
-デザインする者により意図されたもの
・配布されるカリキュラム
-大学管理者により編成されるもの
-教師により教授されるもの
・経験されるカリキュラム
-学習者により学ばれるもの力リキュラムと社会
・力リキュラムは、学習者が将来働く医療サービス、医療コミュニティとの共生を実現すベきであると主張されている。
・カリキュラムの基礎を構成する価値は医療サービスの供給を促進するものでなければならない。カリキュラムと医療コミュニティは相互に高めあう関係にあり、教育が医療サ一ビスを向上させ、医療サ一ビスが教育を向上させるという相互関係がある。学習者は力リキュラムに従って教育を受け学習する。学習者はまた医療コミュニティの中で実習などを通じて学習し、将来の自分の仕事がどのようなものかを知ることができる。
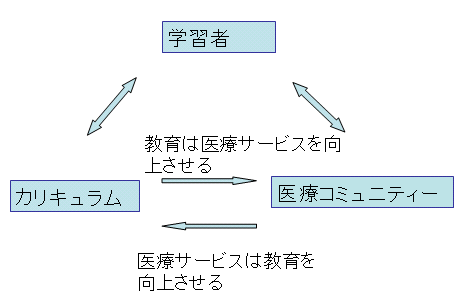
カリキュラム作成ステップ
1)社会的二ーズのアセスメント
力リキュラムを作成する最初のステップは、社会的二ーズのアセスメントである。医師/歯科医師に社会が何を求めているかを明らかにする必要がある。そのためには、医療、保健において対処しなければならない問題、解決しなければならない問題を列挙し、それらに対する解法や研究的アプローチの過程を明確にしなければならないであろう。
2)学習者の二ーズのアセスメント
次のステップが学習者の二ーズのアセスメントである。社会の要請に応えるには何ができるようならなければならないかをリストアップする。より具体的には、、医療、保健における問題に対処し、解決できる能力、すなわち臨床能力は何か、そして、学習前にすでに持っている知識、技能、態度は何かを明らかにすることである。このニーズをとらえる方法にはさまざまなやりかたがある。
最近では、アウトカム(...ができるようになる、ということ)を記述することから、カリキュラム作成を開始することが一般化しつつある。
3)到達目標と個々の測定可能な特異的目標の設定
次のステップは到達目標と個々の測定可能な特異的目標の設定である。
従来、「教育とは行動に変化をもたらすことである」という定義のもと、特異的目標を行動目標behavioral objectiveとして記述することが行なわれて来た。カリキュラムのユニットごとに全般的目標general instructive objective (GIO)を記述し、更により詳細な個別の特異的目標を行動目標specific behavioral objective (SBO)として記述して、カリキュラムを作成し、シラバスとして学習者に配布された。
しかし、行動目標として学習目標を記述することは、時間がかかり、狭い範囲の技能や知識に限定される可能性があり、さらに、行動の面から表現することが難しいため、より高次の思考、問題解決、価値獲得の過程は除外される可能性がある、といった批判がある。その結果、現在では明確に記述された行動目標は、必ずしも力リキュラム作成のゴールドスタンダードとはみなされていない。
4)教授・学習の方略 teaching and learning strategies
次のステップは、教授・学習の方略strategyを決めることである。方略とは方法と戦略のことである。教室での大人数での講義なのか、小人数の実習なのか、小人数の発問型学習(PBL, Problem‐based learning、問題基盤型学習、問題に基づく学習、inquiry learningという用語もある)なのか、宿題はどうするのか、学習成果のアセスメントすなわち試験はどうするのか、形成的試験(formative examination)をするのか、最終的評価(summative examination)はどのような方法で行なうのか、などを決める。
5)コンテンツ作成
次に、コンテンツを作成する。
6)教授と学習の実行
次に、教授と学習が実行される。
7)学習者のアセスメント
次に、評価とフィードバックが行なわれる。評価は学習者の達成度のアセスメントがまず行われる。すなわち試験である。
知識の試験は、Multiple choice questions (MCQ)、技能の試験はOSCE (objective structured clinical examination)が主要な方法であるが、これら以外にもさまざまなアセスメント法がある。
8)カリキュラム評価
学習者からカリキュラムについて評価とフィードバックが行なわれる。
これらのステップは、それぞれのステップにおいて、柔軟に適宜改善されるべきである。
行動目標の表現
使用しても良い動詞
・書く
・説明する
・列挙する、朗読する、暗唱する
・識別する、同定する
・鑑別する、識別する
・解決する
・構成する、構築する
・列挙する、リストアップする
・比較する、比べる
・対比する
使用してはいけない動詞。
・知る
・理解する
・真に理解する、
・真価を理解する、認める
・...の意味をとらえる
・...楽しむ
・...を信じる
・...を信頼するアウトカムに基づくカリキュラム作成
カリキュラム作成のコア: アウトカムに基づくカリキュラム
1)まず最初に、「望まれるアウト力ム(学習者はxxxができるようになる)」を決める
2)内容を決める
3)教授と学習 teaching and learning
4)アセスメント(学習者)
5)評価(力リキュラム)
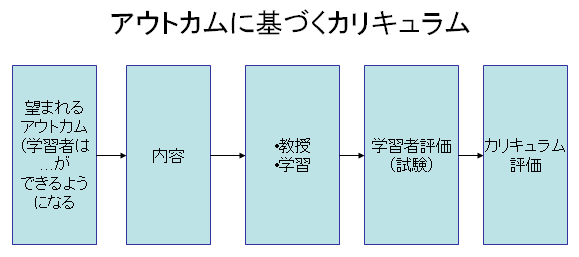
カリキュラムユニットの例:企図の記述の例
企図 intent (目的)
・一般的疾患の治療のための知識と、技能を持った卒業生を育成すること
目標 objectives
・循環器系の一般的疾患の発症機序を識別できる
・循環器系疾患の問診の技能を身につける
広義のアウトカム broad outcomes
・卒業生は、一般的疾患の治療のための知識と、技能を獲得するであろう
・学生は、循環器系の一般的疾患の発症機序を識別できるであろう
・学生は、循環器系疾患の問診の技能を獲得するであろう学習者の視点から見たカリキュラムマップ
カリキュラム作成の際には、学習者の視点からみた場合に、どのように見えるかを考慮する必要がある。例えば、同じアウトカムを目的としたカリキュラムがいくつかあった場合に、どのカリキュラムを学習者が自分に最適であると判断して、選択するかを考えてみることである。
その際に、学習者が考える項目は、1)状況、2)企図、3)内容、4)教授と学習、5)評価試験、6)構成・編成、7)評価の7つである。
・状況とは、そのカリキュラムの内容が、自分の今までの経験、能力、背景に、合っているかどうかということである。
・企図とは、そのカリキュラムが、目的、目標、アウトカムについて、明瞭に、記述しているかどうかということである。
・内容とは、カリキュラムの展望が適切かどうか、各ユニットやコースの順序が適切かどうか、内容が目的を達成するのに適切かどうか、実際との関連が、適切かどうかすなわち実習などが含まれているかどうか、ということである。
・教授と学習とは、教授方法や学習方法に、様々な方法が用意されており、自律学習の機会も十分与えられ、実生活状況での学習すなわち本物の臨床状況での学習など、教授と学習が学習者志向で行われているかどうかということである。
・評価試験とは、形成的試験や総括的試験に、明確な青写真があるかどということである。
・構成・編成とは、カリキュラムのブロックやコース、ユニットや時間割が、明確に、編成され、構成されているかどうかということである。
・評価とは、カリキュラムに対する学習者のフィードバックを得るために、質問票が用意されているかどうか、フォーカスグループによる調査が行われているかどうか、カリキュラムの評価に、学習者が参加しているかどうかということである
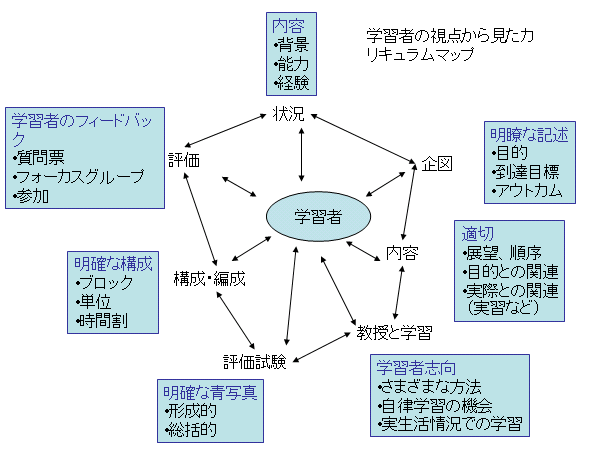
カリキュラム作成時に問うべき10の基本的質問
1.トレーニングプログラムの生み出すものとの関係でニーズは何か?
2.目的と到達目標は何か?
3.どのような内容(コンテンツ)を含むべきか?
4.コンテンツをどのように編成するか?
5.どのような教育方略を採用するか?
6.どのような教授方法を用いるか?
7.学習者の達成度の評価、アセスメント(評価試験)はどのようにして行うか?
8.カリキュラムの詳細をどのようにして伝達するか?
9.どのような教育環境、あるいは教育風土を育成するか?
10.どのようにプロセスのマネージメントを行うべきか?
文献
[1] Prideaux D: ABC of learning and teaching in medicine: Curriculum design. BMJ 2003;326:268-270.
[2] Harden RM: Ten questions to ask when planning a course or curriculum. Medical Education Booklet No 20, Association for the Study of Medical Education, UK, 1999.
[3] Harden RM: Approaches to curriculum planning. Medical Education Booklet No 21, Association for the Study of Medical Education, UK, 1986.